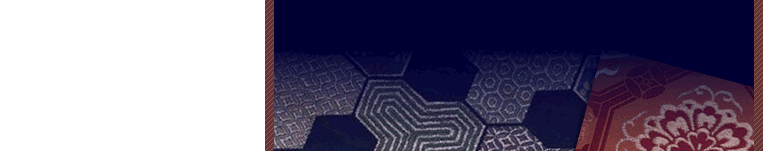「なぁ、ミルーダ、超落ち込んでんぞ」
「はぁ?」
珍しく連れ立って酒場に出かけたファールはシガンの言葉に眉を跳ね上げた。
「あのねぇ……あんたがあの子に平手打ちの一発でもしてりゃ私がわざわざ嫌われ役にならんですんだんだっての」
ファールは不機嫌そうにエールをあおった。
秋のけはひたつまゝに
ミルーダは迷宮の中でミスを犯した。
モンスターの姿を見て自失する。それによりシガンが瀕死の重症を負ったことは確かだ。
「……でも生きてんだから、そんな気にすんなって」
帰るなり食事もとらずにアドベンチャラーズインの部屋に閉じこもり、ドアを開けようとしないミルーダに困ったようにシガンがドアを叩く。
ドアは開かない。
シガンがドアを叩いている。
部屋の隅でミルーダは膝を抱えた。
修練場で教わった冒険者としての最低限のモラルが頭に思い浮かぶ。
『自分が死んだとしても仲間はその死体を担いで冒険を続けることになる。その行為に善も悪も中立も関係ない。自分が死んでそれですむと思ったら大間違いだ。1人が死ぬことによってパーティの戦力が落ちるだけでなく、それを担いで行動することによって仲間の負担も増える。だから冒険者は出来る限り死んではならない。死なないように最大限の努力をしなければならない』……その言葉はとりもなおさず仲間の迷惑になってはならない、ということを意味する。
冒険者として『仲間の迷惑にならない』ということが最低限のモラルなのだ。
なのに……
ミルーダは膝を抱える腕に力を込める。
子供のころより姉は奔放な人間で父親に懐いていたようであったが、ミルーダは敬虔な母親に懐いていた。
……本当に懐いていたのだろうか?
母親は精神的に不安定な人間であり、常に経験であれと子供たちに教え諭していた。
ただ神を崇めることのみを真理と信じ、父や姉が芸術に興味を持つことを『悪魔によって堕落させられている』と嘆き、しかしそれでも『堕落させられ悪魔の尖兵となったものに弱みは見せない』と仲のいい夫婦を演じていた。
だから姉が楽団についていこうとしたとき父親が辟易するほど姉の処断を求めたのは母であり……そこに肉親の情は存在しなかった。
母はミルーダを抱き毎晩のように語り掛ける。
「あなたは天使なのだから、この部屋の外にいる有象無象の悪魔どもに汚されてはだめ」
またミルーダが父と会話をした日の夜などは……
「お前まで悪魔の仲間になるつもりかっ! 私を1人にするつもりかっ!」
とヒステリックに叫びながらミルーダを殴り、蹴りつけた。
ミルーダはただ家族で仲良く暮らしたかっただけなのに、父も姉も知らないところで母にそうやって殴られ続けることだけが家族のバランスを保つ唯一の方法だった。
父は母を貞淑な妻と信じ、客にそう紹介する。母は笑顔で頭を下げながら『悪魔』とさげすむのだ。
ある日、姉が屋敷から脱走する。
父は慌てふためき家人をやって姉を探そうとするが、見つからなかった。
そしてこの日を境に……恐らく姉がいなくなったことが契機になったのだろう母は回復した。
母は悪い夢を見ていたかのように今までのことをすべて覚えていた。そして自分の夫、そして腹を痛めて産んだ実の子を悪魔と信じていたことを後悔し嘆き悲しんだ。
ミルーダが母を慰めようとすると、ミルーダの目の前を星が飛んだ。
星?
ミルーダは一瞬自分が殴り飛ばされたことに気がつかなかった。
母は倒れたミルーダに対し殴りかかる。
丸くなって耐えようとする彼女に投げかけられた母の言葉をミルーダは一生忘れることはないだろう。
「お前があの子が悪魔じゃないって教えてさえくれれば! あんたは私の実の娘を悪魔じゃないって知ってたんだろう! そして知りながら娘を蔑む私の姿を見てあざ笑っていたんだろう! 悪魔! お前こそが悪魔だ!」
ミルーダに彼女を弾劾することなど出来なかった。
彼女はそれで精神に均衡をとろうとしているのだ、と気づいてしまったから。
だからミルーダは父も使用人たちも知らないところで母親の虐待を受け続けることになる。
春の日も。
夏の日も。
秋の日も。
冬の日も。
また巡って春の日も。
しかしミルーダはもうすでに限界が近づいてきていた。
母はもう夫に対し、限りなく貞淑な妻であり、母のことを知っているのは自分だけだったのだから……だからもう自分が家を出ても大丈夫だと思った。
自分がリルガミンに遊学にいきたい、と言ったとき、父はそのころには姉の件があったためずいぶんと丸くなっており簡単にそれを許し、ミルーダはリルガミンで新しい生活が始められる、はずだった。
しかし遊学先の神殿に母親の手紙が届けられる。
『どこへ逃げても無駄だ。悪魔め』……ミルーダは天を仰ぎ、寄宿先を出て母親から逃げようとした。
そのときに目の前にあったのが冒険者修練場だった。
だから自分はなにかの目的があって冒険者になろうとしたんじゃない。崇高な目的なんてなにもない。
ただ逃げただけ、だ……
タイロッサムにそれを見透かされたときミルーダは母親にまた殴られることを思い恐怖していた。
自分は逃げているだけ……
ドカン!
部屋のドアが吹き飛んだ。
その向こうにはシガンが槍を構えて立っている。
殴られる! 殴られる! 殴られる!
私が悪い子だから殴られる!
身を硬くするミルーダにシガンがゆっくりと近づき……
「よし、腹減ったからメシ食いに行こうぜ」
ミルーダの頬に手を添え、明るくそう言った。
ミルーダはシガンを見上げる。その目から涙がこぼれた。

 カレンダー
カレンダー